【小三小四】年度はじめに集団生活のルール・約束を確認しよう
関連タグ
中学年になると、自分たちでできることが増え、活動が活発になってきます。一方で、生活や学習のルールがあいまいになってしまうことがあります。年度当初に、みんなが気持ちよく過ごすためのルールを、しっかり確認しておきましょう。確認をするときには、どこまでが学校、学年のルールで、どこからが学級のルールとしてよいのか、他の教職員と確かめておきましょう。
執筆/神奈川県公立小学校教諭・杉本竜太
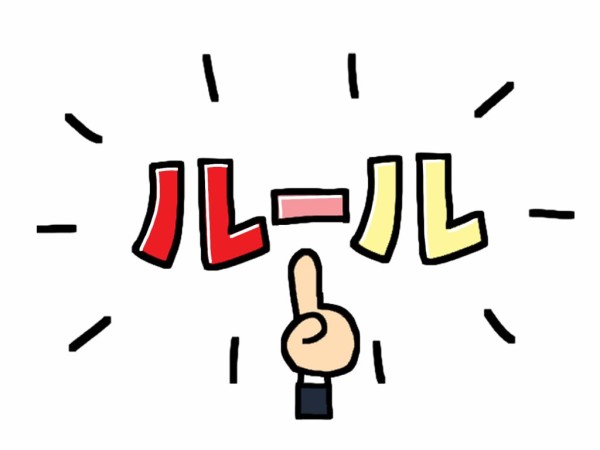 イラストAC
イラストAC 目次
ルールを伝えるときのポイント持ち物について学習についてルールを伝えるときのポイント
ルールを守って生活する子供を育てるためには、子供たちが学校のきまり(ルール)の意義を理解することが大切です。
まず、全員が気持ちよく生活をするためにルールがあり、一人ひとりがそれを守ることが大切であることを、子供たちに話しましょう。

持ち物について
筆箱や道具箱の中身など、学校生活に必要な物しか持ってきてはいけないことや、持ち物に記名することなどの確認が必要です。
三年生では、習字セットや絵の具セット、リコーダーなど、学習で使う道具が増えます。また、副読本などを使う場面も増えるので、何を持ち帰り、何を学校に置いておくのか、確実に子供たちに伝えましょう。学校に置いてよい物に関しては、どこに置けばよいのか明確にしておきましょう。
四年生では、クラブ活動が始まります。クラブによっては、自分で用具などを持ってくることがあります。そのような場合の保管場所や約束事項についても確認しておきましょう。

学習について
この記事には続きがあります。小学館IDでログインすると最後までご覧いただけます(残り: 342 文字)
 1 すぐできるシンプル学級レク!42種まとめ
1 すぐできるシンプル学級レク!42種まとめ  2 2~4人で挑戦!運動会を彩る安全な組体操技25選
2 2~4人で挑戦!運動会を彩る安全な組体操技25選  3 小5 国語科「きいて、きいて、きいてみよう」全時間の板書&指導アイデア
3 小5 国語科「きいて、きいて、きいてみよう」全時間の板書&指導アイデア 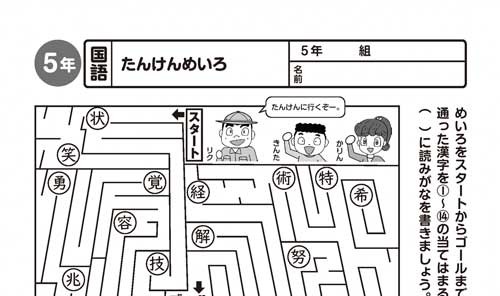 4 小学5年生の考える力を伸ばす!国語・算数おもしろパズルプリント
4 小学5年生の考える力を伸ばす!国語・算数おもしろパズルプリント  5 2025年度春新曲運動会ダンス|カンタンで映える振り付け解説【PR】
5 2025年度春新曲運動会ダンス|カンタンで映える振り付け解説【PR】 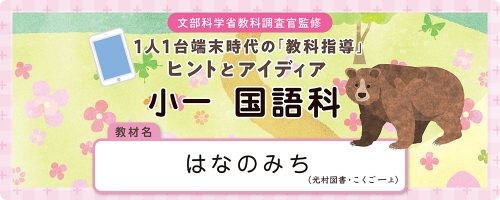 6 小1 国語科「はなのみち」板書例&全時間の指導アイデア
6 小1 国語科「はなのみち」板書例&全時間の指導アイデア  7 ニューノーマル時代の”組まずにつくる”組体操の技
7 ニューノーマル時代の”組まずにつくる”組体操の技 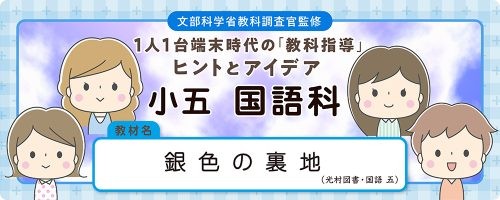 8 小5国語科「銀色の裏地」全時間の板書&指導アイデア
8 小5国語科「銀色の裏地」全時間の板書&指導アイデア 
